皆さんは本屋さんに行ったとき、どの本を買うかと本選びに困ったことはありませんか?
本屋さんには本がたくさんありすぎて、どの本を買ったらいいのか迷いますよね!
実は、本の選び方にはコツがあるのです!
今回は、失敗しない本の選び方のコツをお教えします。
ちなみに私は本屋さんに行くと2時間以上は滞在します!!
また、最近は読書をする人が減っていますし、子供の読書量も減っています。
子供の読書に関する現状などを知りたい方はこちらをご覧ください。
また、読書はアウトプットが大切です。
記憶に定着するアウトプットについては、こちらの記事を参考にして頂ければと思います。
本の選び方にコツはあるの?
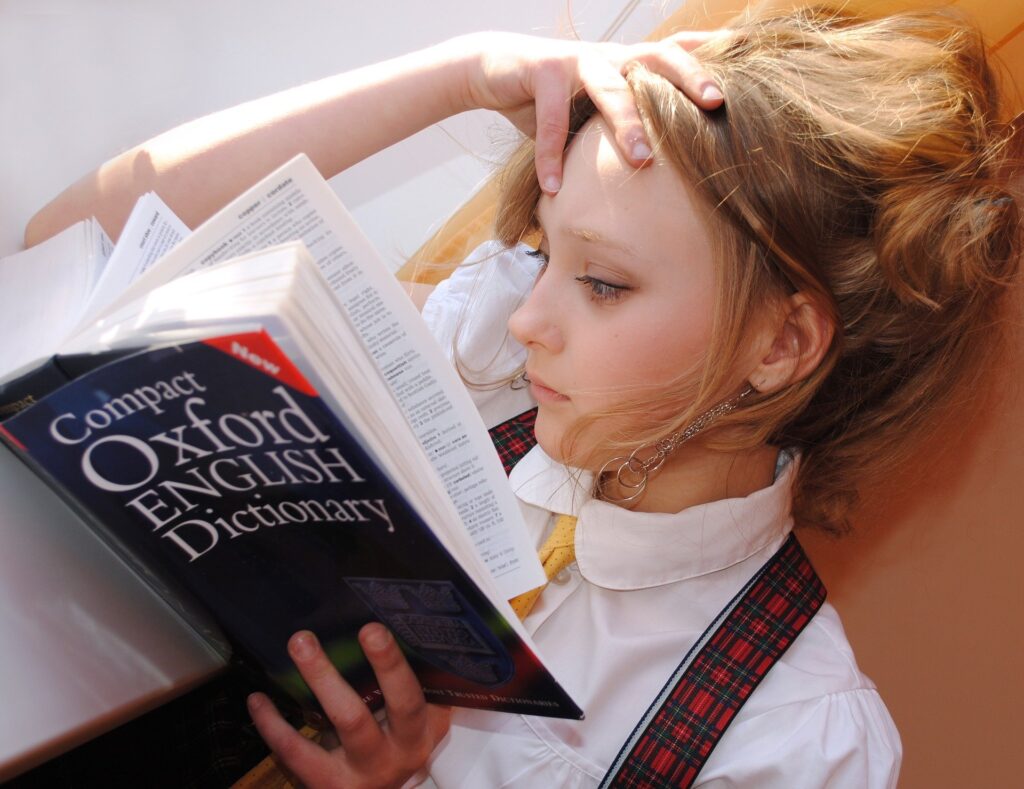
どんな本を読もうかと迷ったあげく、いざ買ってみると「失敗した」と思ったことはありませんか?
本の選び方に失敗をした経験がある方は、これからご紹介する「本の選び方のコツ」をご覧になってください。
正しい本の選び方を知ることで、失敗をする可能性が減ります。
本を読む目的を決める
本の選び方のコツは「本を読む目的を決める」です。
まず、あなたが本を読む目的はなんですか?
仕事に役立てるために読むのか?趣味として読むのか?
勉強のために読むのか?などと
自分が本を読むことに何らかの目的があるはずです。
その目的から逆算して、
「今の自分にとって読むべき本はなんなのか?」を決めましょう!
読みたいジャンルを決める
本の選び方のコツに「読みたいジャンルを決める」があります。
本を読む目的を決めた後は、次にどんなジャンルの本を読むか決めましょう。
仕事に役立てたい場合
仕事に役立てたい場合は、あなたの職種に役立つビジネス書や業界の本などを読むのもいいでしょう。
営業をしている人なら、心理学の本やコミュニケーションスキルを磨ける実践本などを読むのもいいでしょう。
また、これはあくまで私のビジネス書を選ぶ基準ですが、「科学的根拠がないものはできるだけ選ばない」ことにしています。
「この方法なら成功できる!」的な本は一例としては参考になりますが、全員に当てはまるわけではありません。
また、果たしてそれが本当にその作者が言っていることが要因なのか?と、疑問に感じてしまいます。
その人には見えていないなんらかの他の要因があるかもしれません。
なので、私はビジネス書などを選ぶ場合は、研究結果がしっかりと記載されていたり、根拠があるかどうかも本を選ぶ判断基準のひとつにしています。
趣味として読む場合
趣味で読む場合は、興味のあるテーマから選んで読むのがいいでしょう。
私は結局は自分の興味のある本でなければ、読む気になりません。
おそらく皆さんもそうだと思います。
その興味の中でも、「自分の詳しい分野を深堀りするため」と「興味はあるけど詳しくない分野」に分かれます。
この2つを軸にして考えると、本選びが楽になると思います。
売れている本を買う

本の選び方のコツに、売れている本を買うというのもあります。
売れている本を買うという事のメリットは「ハズレが少ない」という事です。
世の中に本はたくさんあり、面白くないものや書いている内容が微妙なものもあります。
そんな中、売れている本というのはみんなが買っているということですから、
面白かったり、最近の話題をテーマにして書かれたりしています。
また、有名な人や影響力のある人の本が売れるので、
そういう方の新作本を読むことで、過去の作品も気になり、次の本選びが楽になるというメリットがあります。
どんな人が書いた本かを見る
本の選び方のコツに「どんな人が書いた本かを見る」があります。
「どんな人が書いた本か?」これは私が本を選ぶ際に必ず見るポイントです。
この情報化社会で世の中に情報があふれている中、私たちに必要なのは正しい情報を得ること。間違った情報に惑わされないことです。
その為にも、誰が書いた本なのかは重要になります。
例えば、病気の治し方についての本があったとして、その本が医師免許を持っていない一般人だったらどう思いますか?
「本当にこの人のいう事を信用していいのだろうか?」となるはずです。
なので、どんな人が書いた本なのかを知ってから買うようにしましょう。
本のレビューを見てみる
本の選び方のコツに「本のレビューを見る」があります。
今は本屋さんに行かずネットで本を注文したり、電子書籍で読む人も増えています。
そんな中で便利な本の選び方として、Amazonなどの評価・レビューは参考になります。
Amazonのレビューを見てみるとわかりますが、結構要約された内容の感想を見かけたりするので、私も本を買うときは参考にしたりします。
その理由として、本を読んでアウトプットをするためにAmazonのレビュー欄を利用している人がいるからだと思います。
本の内容を記憶に定着させるには、アウトプットがいいとされています。
そのアウトプットをするためには、頭の中で内容を整理して、要約しないといけませんから、本を選ぶ側としては非常に参考になります。
立ち読みしてみる

書店で本を選ぶ場合、立ち読みをしてパラパラとページをめくり、自分が読みたい本なのかを選ぶことができます。
立ち読みして本を選ぶ際のポイントは次の通りです。
作者がだれか?
上記でも書きましたが、作者が誰なのかは本選びでとても重要です。
世の中にあふれる本の中で、その本を書いている人が信用できる人か?
正しいことを書いている人かを見分けるためにも、作者を知ることは本選びの大切な要素の一つです。
「まえがき」「あとがき」を見る
本の最初と最後に作者や推薦者が書いている「まえがき」「あとがき」も本選びにおいて重要です。
「まえがき」とはその本の「簡単な要約」や「伝えたいこと」が書いてあります。
その本がどんなテーマなのか?どういう人に向けて書いた本なのか?
作者がどんなことを伝えたいのか?
こういったことが「まえがき」には書かれています。
つまり、「まえがき」見ることで、その本の大まかな内容がわかることになります。
「あとがき」とはその本を読んでくれた方へのメッセージなどになります。
本によって書かれていることが変わりますが、だいたい「本を書いた感想」や「作品に対する思い」など書かれています。
また、本編の内容を振り返ったりするので、本編のまとめ的な役割も果たすことがあります。
そしてわざわざ「あとがき」に書く内容という事は、作者がその本の中で一番伝えたい事でもあります。
つまり、「あとがき」を見ることで、作者が一番伝えたかったことを知ることができます。
目次を見る
本を選ぶとき、目次を見る人は多いと思います。
「どんなことが書かれているのか?」
「自分の興味のあるところはあるのか?」
といったことが目次を見るとすぐにわかるからです。
目次で気になるところや知りたい内容のところが少しでもあれば、その本を買うことは良い選択だと思います。
ちなみに私は、目次で1つでも興味のあるところは、他の内容に興味がなくても買うことにしています。
なぜなら、その1つだけでも自分の頭に知識として入る、もしくは学びになるのなら、その本1冊分の価値があると考えているからです。
本1冊全部読み切っても「この本あまりよくなかったなあ」と思うこともあります。
それに比べると、1つでも自分にとって学びになるのなら、目次で気になった内容だけ読んでも十分だと言えます。
まとめ
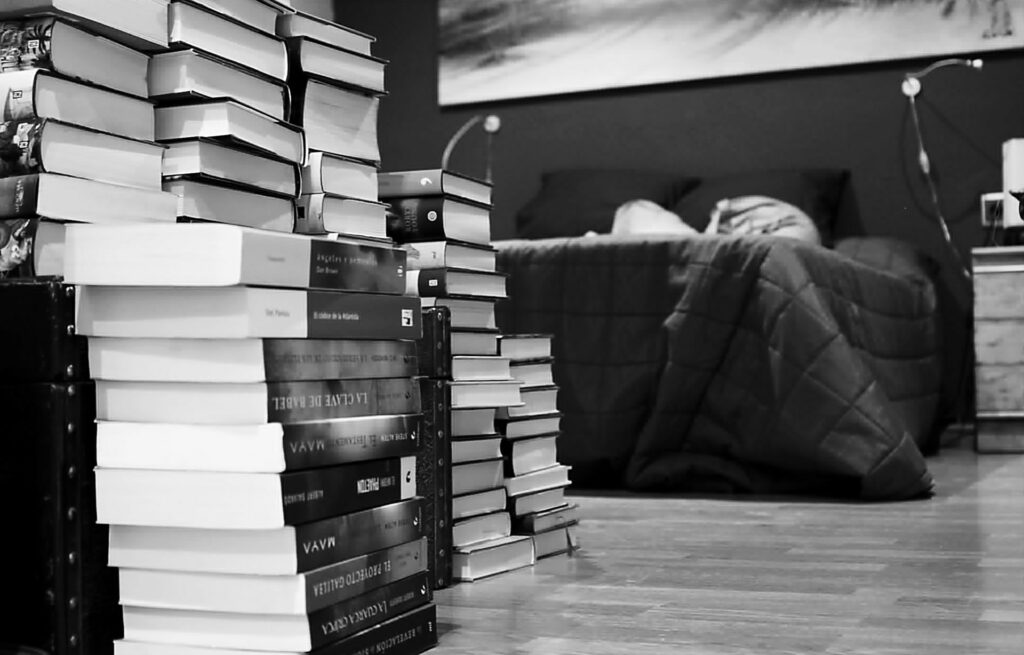
今回は本の選び方のコツについて紹介しましたが、最後に本選びで私が一番大切だと考えていることを書きます。
それは「どんな本であれ、少しでも気になった本があれば買ってみる」です。
これまで本の選び方について書きましたが、「本を選ぶこと」「本の読み方」に決まりはないのです。
自分の興味のある本を興味のあるところだけ読めばいいと思っています。
買った本を最後まで読まなければいけないルールはありませんし、誰かに怒られるわけでもありません。
無理に読もうとしたり、本を選ぶことに失敗しないように慎重になりすぎたりしていては、
本を読むことが嫌いになったり、結局本を買わなかったりします。
ぜひ、気軽な気持ちで本を手に取り、読書を楽しんでもらえたらと思います。
読書をしたいけど「本を読むと疲れる」ことはありませんか?
その場合、読書の姿勢が悪いのかもしれません。
姿勢が悪いと肩こりや首が痛くなったりして、読書に集中できません。
読書をすると疲れるという方は、こちらの記事で読書で疲れない姿勢を紹介していますので、ぜひご覧ください。
最後までご覧いただきありがとうございました!



